
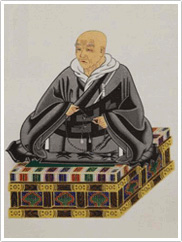
| 本尊 | 阿弥陀如来 |
|---|---|
| 正依の経典 | 仏説無量寿経(大経)、仏説観無量寿経(観経)、仏説阿弥陀経(小経) |
| 宗祖 | 親鸞聖人(1173~1262) |
| 宗祖の主著 | 顕浄土真実教行証文類(教行信証) |
| 宗派名 | 真宗大谷派 |
| 本山 | 真宗本廟(東本願寺) |

顕浄土真実教行証文類(教行信証)親鸞聖人の主著であり、浄土真宗の根本聖典で、『教行信証』と略称されています。教巻・行巻・信巻・証巻・真仏土巻・化身土巻の6巻からなっており、冒頭に総序、信巻の前に別序、巻末には後序が置かれています。


正しくは正信念仏偈と言います。お経ではなく、親鸞聖人が『教行信証』行巻の中に著わされた60行120句の偈文で、聖人がお念仏の教えに出遇った感動を述べられています。浄土真宗のご門徒は、朝晩お内仏(仏壇)の前でお勤めし、毎日親鸞聖人のお言葉をいただきます。
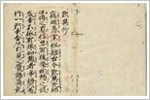
親鸞聖人の弟子である唯円(ゆいえん)が著したと言われる書であり、親鸞聖人の言葉によりながら、聖人なきあとの異説を歎き、聖人の教えの真意、真実の信心を伝えようと書き記したと言われています。前後2部に分かれ、前半は、親鸞聖人から聞いた法語を記し、後半では、当時行われていた念仏の異議をあげて批判し、真実の信心に目覚めるように、法然上人や親鸞聖人の言行が引かれています。

第8代蓮如上人が、ご門徒たちに宛てた「御手紙」で、真宗の教えがわかりやすく、しかも簡潔に書き表されています。当時(室町時代)の「御文」は、ご門徒に広く公開され、法座につらなった読み書きが出来ない人々も、蓮如上人の「御文」を受け取った人が拝読するその内容を耳から聴いて、聖人の教えを身に受け止めていかれました。「御文」は、現在約250通が伝えられており、その中で、文明3年(1471年)から明応7年(1498年)にわたる58通と、年次不明の22通の合計80通を5冊にまとめた『五帖御文』が最もよく知られています。

親鸞聖人の曾孫である覚如上人が撰述した聖人の行状絵巻。図画の部分を軸装したものを「御絵伝」と称し、寺院の報恩講期間中、本堂の内陣余間に奉掛されます。詞書の部分を集めたものを『御伝鈔』と称し、真宗本廟(東本願寺)をはじめ各寺院で勤められる報恩講の際に拝読されます。

報恩講とは、宗祖親鸞聖人の御祥月命日に勤められる法要のことです。祖師の御祥月命日や御命日に報恩の仏事を勤めることは真宗独自のものではありませんが、真宗門徒にとっては一年でもっとも大切で中心となる仏事として勤められてきました。
報恩講は親鸞聖人滅後、門弟らが聖人の御命日にお勤めをしたことに始まります。当時は「報恩講」と称していませんでしたが、宗祖三十三回忌の際には、第3代覚如上人が『報恩講私記(式)』をお作りになって法要次第を調えられ、後に覚如上人の子・存覚上人が『歎徳文』をお作りになって法要次第に加えられました。そして第8代蓮如上人の頃には各地の寺院・道場でも広く勤まるようになりました。
しかしその源を尋ねれば、親鸞聖人御自身、師・法然上人の御命日に人々と寄り合い、仏法を聴聞し、お勤めをしておられたことにあるといえます。聖人は生涯、日々に新しく、感動をもって法然上人がお説きになった念仏の教えを聞き、そして語り合っていかれたのですが、その大切な機会が法然上人の御命日の集い(講)であったとうかがわれます。御命日にお勤めをしつつ、法然上人の教えをいよいよ深くいただいていかれた、この親鸞聖人のお姿こそ、いま私たちがお勤めしている報恩講の原点です。
思えば、私たちが生きていくうえには親の恩や師の恩など、いろいろなご恩があります。それぞれ大切なことですが、報恩講の恩とは、なにより親鸞聖人がいただかれた念仏の教えに遇い、自らが生きる依りどころを教えていただいたご恩のことです。そのご恩に報謝し、いよいよ親鸞聖人が明らかにされた真実のみ教えを聞信し、共に念仏申す身となっていくことを誓うことが報恩講の大切な意味であります。

帰敬式は、古くから「おかみそり」ともいわれ、人として生まれた意義と生きる喜びを見出したいと願う私たちにとって、如来の教えを依りどころとして生きる、歩みの出発を期す大切な儀式です。この帰敬式では、「おかみそり」を受け、仏・法・僧の三宝に帰依することを誓い、法名をいただきます。
仏・法・僧の三宝に帰依するとは、自ら真実に目覚め、その真実の教えを説かれた釈迦如来をはじめ諸仏(仏)に帰依し、その教え(法)を大切に聞き、あらゆる人々と共に同朋の交わり(僧:僧伽《サンガ》)を実現せんと願うことです。また、法名とは、如来の教えを依りどころとして人生を歩む仏弟子としての名のりを表すものです。
「ご本尊(お内仏)」を中心とした、念仏申す生活の中に、如来の本願のおこころを聞きひらき、あらゆる人々を御同朋御同行として敬われた親鸞聖人を宗祖と仰ぎ、共に仏道を歩む真宗門徒になろうとする出発式が帰敬式です。
| 時代 | 真宗大谷派(東本願寺)教団略史 | |
|---|---|---|
|
平安後期
|
1173 | 親鸞誕生。 |
| 1181 | 親鸞(9歳)、慈円のもとで出家。 | |
|
鎌倉時代
|
1198 | 親鸞(29歳)、これまで堂僧を勤めた延暦寺を出て、六角堂に参籠、聖徳太子の夢告により源空(法然上人)の門に入る。 |
| 1207 | 専修念仏停止の院宣くだり、源空と門弟処罰される。 親鸞(35歳)、越後へ遠流。(承元の法難) |
|
| 1211 | 親鸞(39歳)、流罪を許される。 | |
| 1214 | 親鸞(42歳)、上野国佐貫で三部経千部読誦を発願するが、中止して常陸へ赴く。 | |
| 1224 | この頃、親鸞『教行信証』著作。 | |
| 1235 | 親鸞、この年までに関東から京都に帰る。 | |
| 1262 | 親鸞(90歳)、京都の住居で病臥、入滅。 京都東山鳥辺野にて火葬する。 |
|
| 1272 | 覚信尼、親鸞の遺骨を東山大谷の地に移し、廟堂を建立して親鸞の影像を安置。 | |
|
室町時代
|
1415 | 蓮如誕生。 |
| 1461 | 蓮如(47歳)、初めて『御文』を書いて門徒を教化。 | |
| 1465 | 東山の大谷本願寺、延暦寺衆徒により破却される。(寛正の法難) | |
| 1468 | 蓮如(54歳)、三河を巡教。 | |
| 1471 | 蓮如(57歳)、越前吉崎に赴き、坊舎建立。 | |
| 1473 | 蓮如(59歳)、『正信偈』・『三帖和讃』開板。 | |
| 1480 | 蓮如(66歳)、山科本願寺上棟。 | |
| 1497 | 大坂に石山坊舎(後の石山本願寺)完成。 | |
| 1499 | 蓮如(85歳)、山科にて入滅。 | |
| 1563 | 三河一向一揆起こる。 | |
|
安土桃山時代
|
1591 | 本願寺、京都七条堀川の地へ移る。 |
| 1602 | 教如、家康より京都烏丸六条に寺地を寄進される。(東本願寺成立・東西分派) | |
|
江戸時代
|
1788 | 東本願寺両堂など焼失。(天明の大火) |
| 1798 | 両堂再建。(寛政度) | |
| 1823 | 東本願寺両堂など焼失。 | |
| 1835 | 両堂再建。(文政度) | |
| 1858 | 東本願寺両堂など焼失。 | |
| 1860 | 仮両堂再建。(安政度) | |
| 1864 | 東本願寺両堂など焼失。(蛤御門の変) | |
|
明治時代
|
1885 | 相続講を設立する。 |
| 1895 | 両堂再建。(明治度) | |
